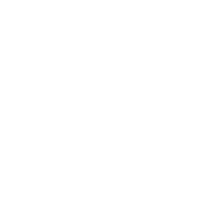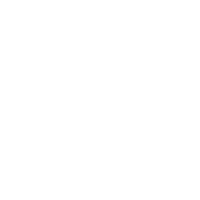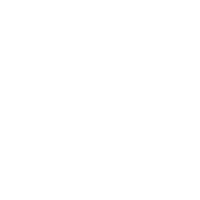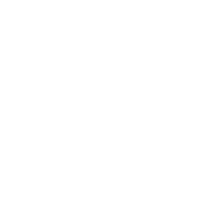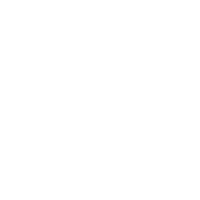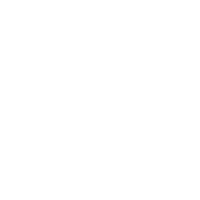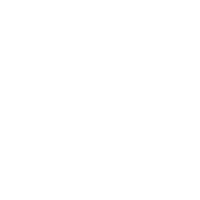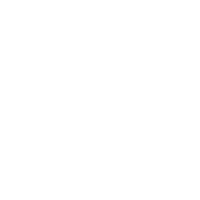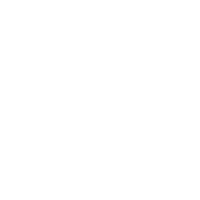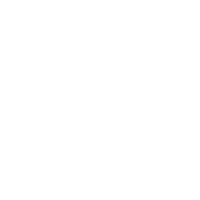一般眼科

- 目がかゆい
- 目が充血している
- 見え方に違和感がある
視力低下やアレルギー性結膜炎、角膜炎、ものもらいなど、目の症状全般を診療します。先進の検査機器で丁寧に検査を行い、病気の早期発見と早期治療に努めています。目の病気は進行させると視力の回復が難しい場合があるため、目に違和感を覚えたら早めにご来院ください。
さらに高度な検査や治療が必要な方には、連携医療機関をすみやかにご紹介いたします。
主な眼科検診
・視力検査・眼圧検査・屈折検査・色覚検査・視野検査・アレルギー検査・眼科検診・定期検診・幼児、児童の眼科検診・成人の眼科検診
白内障

- 視界がかすむ
- 日差しや電灯の光が
異常にまぶしい - ものが二重になって見える
白内障とは、目の中でレンズの役割をしている水晶体が白く濁って見えにくくなる病気です。主な原因は加齢で、個人差がありますが誰でも歳を重ねるにつれて症状が出てきます。
初期の段階は点眼治療で進行を抑え、進行している場合は手術で視力の回復をめざします。当院では大学病院で教授を務める経験豊富な眼科医による日帰り手術を行っています。お気軽にご相談ください。
緑内障

- 視界が欠ける
- かすんで見える
- 視野の一部が黒くなって見える
緑内障とは、何らかの理由で「眼圧」が上がり、視神経が圧迫されて視野や視覚に障害が起こる病気です。慢性緑内障はゆっくりと視野が狭くなっていきますが、反対の目が視野を補うため、ご自身では気づきにくいのが特徴です。症状が進むにつれて視野の欠ける範囲は広がり、日常生活がスムーズにできなくなってしまいます。
一方、急性緑内障は急激に眼圧が上がり、片目の強い痛みや充血のほか、頭痛や吐き気などの症状がはっきりと見られます。
主な検査

慢性緑内障は自覚症状が出るころには進行してしまっているため、早期発見をするには検査が欠かせません。また、進行度合いや治療効果を把握するためにも、定期的に検査を行います。
眼圧検査
緑内障の原因となる眼圧を調べる検査です。角膜に空気を吹き付けることで、目に触れることなく眼圧を測定できます。当院では従来のものよりも風圧が穏やかな測定器を使用していますのでご安心ください。
眼底検査
緑内障になると、視神経が眼球とつながっている視神経乳頭のへこみが広がります(視神経乳頭陥凹拡大)。眼底検査ではこの度合いを調べます。
視野検査
視野の範囲を調べる検査です。視野欠損の有無やその範囲を調べることで、緑内障の進行度合いがわかります。
網膜の断層検査
光干渉断層計(OCT)を使って、網膜の断層画像を撮影します。緑内障では視神経周りの網膜が薄くなるため、断面図を撮影することで緑内障を診断することができます。
網膜疾患

- 視野の中心が暗い
- ゆがんで見える
- 黒い点や虫が飛んでいるように
見える
網膜とは目に入ってきた光を眼球の奥で受け止めて、視覚情報として脳に伝える役割を担っている組織です。毛細血管が集中しており、この血管が切れたり詰まったりすると視野や視覚に障害を起こします。また、加齢やケガによって網膜がはがれてしまうこともあります。
当院では網膜疾患の診療を得意とする眼科医が担当しますので、検査や治療法についてもお気軽にご相談ください。
当院でできる網膜疾患治療について

当院では、加齢黄斑変性症、糖尿病網膜症、網膜静脈網膜症に対して、抗VEGF薬治療とレーザー治療を行なっております。
眼鏡処方

- 眼鏡を作りたい
- 今の眼鏡が合わない
目が疲れやすいのは、お使いの眼鏡が合っていないせいかもしれません。個人差がありますが、一般的には眼鏡は2年から3年に1度の頻度で視力に合わせて作り変えることが推奨されています。
当院では目の検査をしっかりと行い、視力だけでなく仕事内容など目の使い方に合わせた眼鏡を処方いたします。
コンタクトレンズ処方

- コンタクトレンズを作りたい
- コンタクトレンズが合わない
- 目の状態に合った
コンタクトレンズがほしい
コンタクトレンズは眼球に密着させるため、目に合わないものや不衛生なものを使うと、目の病気や視力低下を引き起こすことがあります。そのためコンタクトレンズを使用する場合は、定期的に眼科で視力や目の健康状態、適切な使用方法などを確認していく必要があります。
当院では「遠近両用コンタクトレンズ」など、さまざまな種類のコンタクトレンズを扱っておりますので、今のコンタクトレンズが使いにくいと感じている方もご相談ください。
翼状片

- 目がゴロゴロする
- 瞬きをすると痛む
結膜(白目の部分)近くの細胞が異常増殖して、角膜(黒目の部分)に入り込んでしまうのが翼状片です。血管を多く含む結膜が、本来血管のない角膜に侵入するため、黒目が充血したように見えます。
当院は翼状片切除の日帰り手術に対応しています。15分〜25分程度の時間で終了する手術ですので、気になる症状がある方はまずがご相談ください。
レーザー治療

- 術後に白内障が再発した
白内障手術を受けてからしばらくして、目のかすみや視力低下など白内障に似た症状が起きる場合があります。これは「後発白内障」と呼ばれ、手術後に水晶体嚢が濁ってくることが原因です。水晶体嚢の濁りは白内障手術を受けたすべての方に見られますが、自覚症状がなければ特に治療は必要ありません。
当院ではYAGレーザーによる後発白内障の治療を行っています。レーザー光を目に照射するだけで、ほとんど痛みもありません。片目で約5分と短時間で終わり、その日のうちにお帰りいただけます。
眼精疲労

- 目が疲れやすい
- 目がかすむ
- 目が疲れて視力が落ちる
眼精疲労とは、休憩を取っても治らない目の痛みやかすみ目などの症状のことです。進行すると頭痛や食欲不振、吐き気、だるさなど、全身の症状を起こすこともあるため、放置せずに適切な治療が必要です。
当院では点眼や服薬治療のほか、眼精疲労の原因から取り除けるように、新しい眼鏡の処方やスマートフォンの使い方などをアドバイスすることもあります。
ドライアイ

- 目が乾きやすい
- 目がしょぼしょぼする
- 目が疲れやすい
ドライアイは涙の量や質が低下することで起こります。睡眠不足やストレス、長時間のパソコン・スマートフォンの使用、加齢など原因はさまざまです。また、服用している薬の副作用によってドライアイになることもあります。
当院では目の表面や涙の状態を検査し、原因に合わせた治療を行います。市販の目薬では改善がみられない方も、お気軽にご相談ください。
斜視・弱視(小児眼科)

- お子さまの片目が寄っている
- お子さまが近寄って
テレビを見ている - 検診で斜視・弱視と診断された
斜視とは片目は正面を向いているのに、一方の目は別の方向を向いてしまう状態です。原因によって、眼鏡による矯正または手術で治療を行います。お子さまだけでなく、大人の方の斜視もご相談ください。
弱視とは、視力が発達する時期に何らかの原因で見る刺激を脳が受け取れず、視力の発達が妨げられて眼鏡をかけても視力が矯正できない状態です。弱視の治療にはタイムリミットがあり、原因に合わせた治療を早期に行うことが大切です。
斜視・弱視ともに「もしかして」と思ったら、迷わす受診するようにしましょう。当院では専門の視能訓練士が在籍しておりますので、お気軽にご相談ください。